

明石しおさいライオンズクラブ主催の 子ども食堂が始まりました。
今日で3回目。
毎月第3土曜日10時半から 会場は複合型交流拠点ウィズあかし アスピア北館8回調理実習室です。
子ども食堂ですが 調理実習室でみんなで料理を作ります。
料理作りは、頭を活性化させます。
計量は算数、盛り付けは美術の感覚が養えます。
水1mlは=1cc=1グラム 小さじ5mlは5g 大さじはその3倍で15ml
大さじ3だったら 45ml
油は軽いから 大さじ1は13.5g お味噌だったら・・・?
という風に 子ども達に聞きながら計って貰いました。
数字だけでは実感できない子どもがいますが、実際に計量すると体感出来て感覚が養えます。
机に向かう勉強と料理を別物にする必要はありません。
調理は食べ物を 身体に摂取しやすい形にするにことで 頭を使います。
でも試食というご褒美が待っている楽しい実験や体験になります。
火傷や包丁で怪我をしないように気をつけるので、注意力も養えます。
目の前に見えている事だけでなく、次の作業を想像しながら、創造するという 五感全部を駆使する作業です。
机の前に座る勉強では得ることが出来ない勉強が出来ます。
子どもたちは料理を作るのが大好きです。
大人は 子どもが机の前の勉強する事を好みますが、食育の大切さも感じて欲しいと思います。
食べる事は生きる基本です。
与えられるだけでは生きる力は身につきません。
難しい事はさておき、今日も子どもたちの笑顔に接する事が出来て 嬉しい一日でした!
スイカメ 🐢作ってみました。
子どもたち喜んでくれたようです🎶








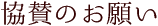


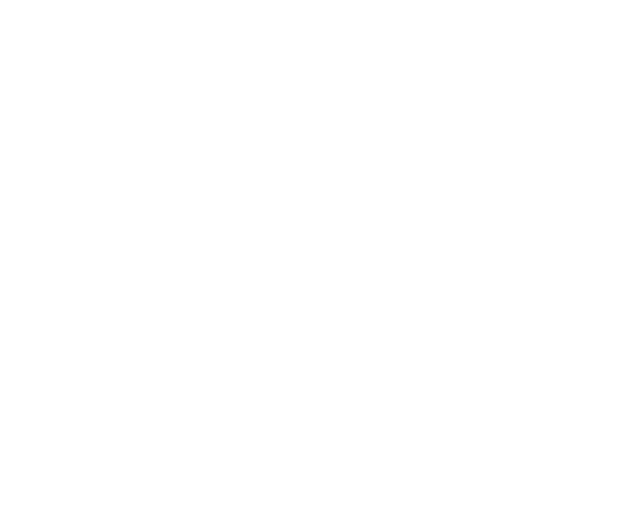

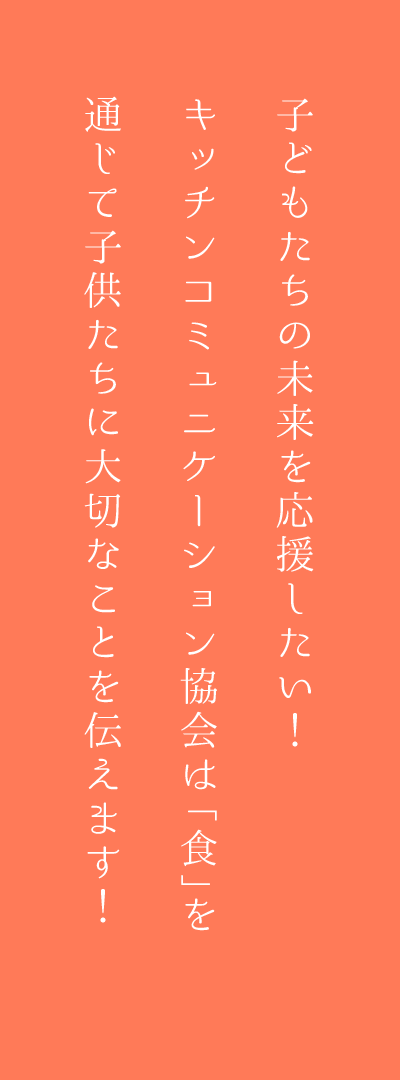

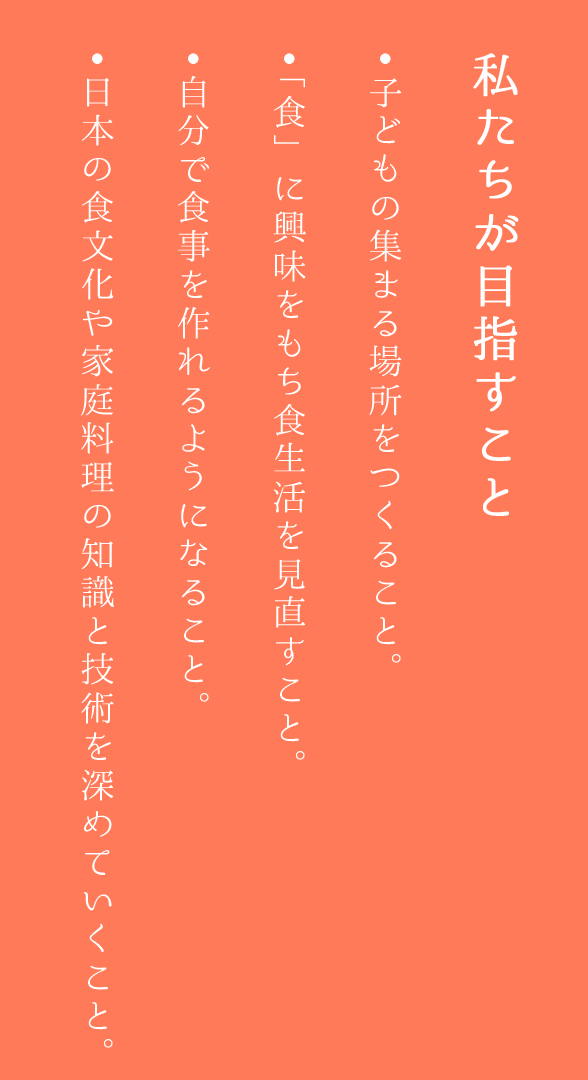










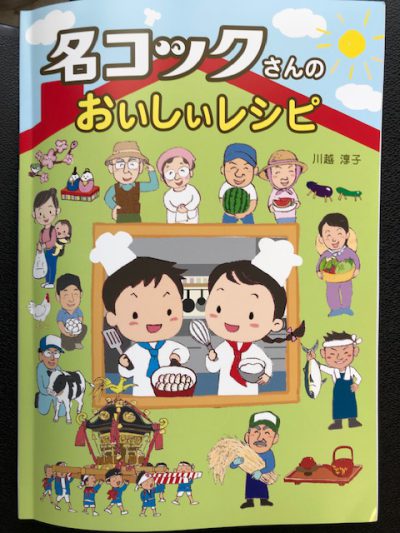
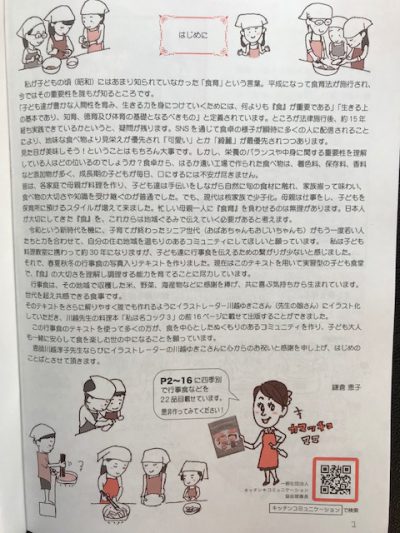
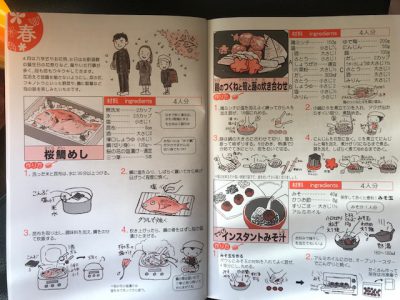
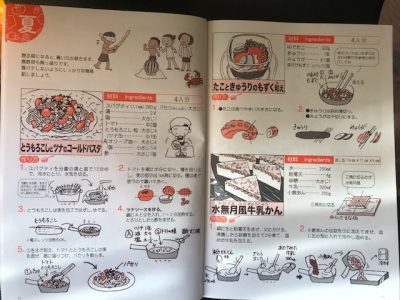
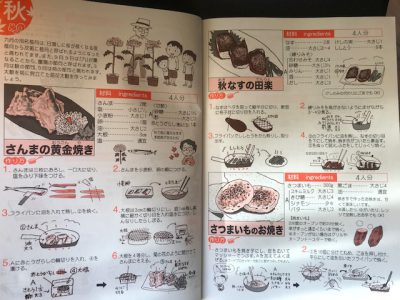
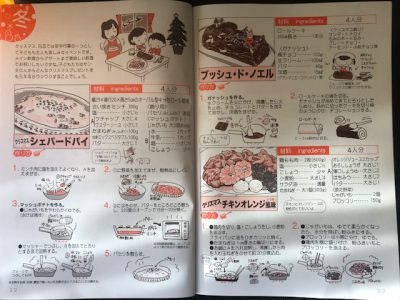


 五月はみんなで味噌玉作り♬
五月はみんなで味噌玉作り♬












